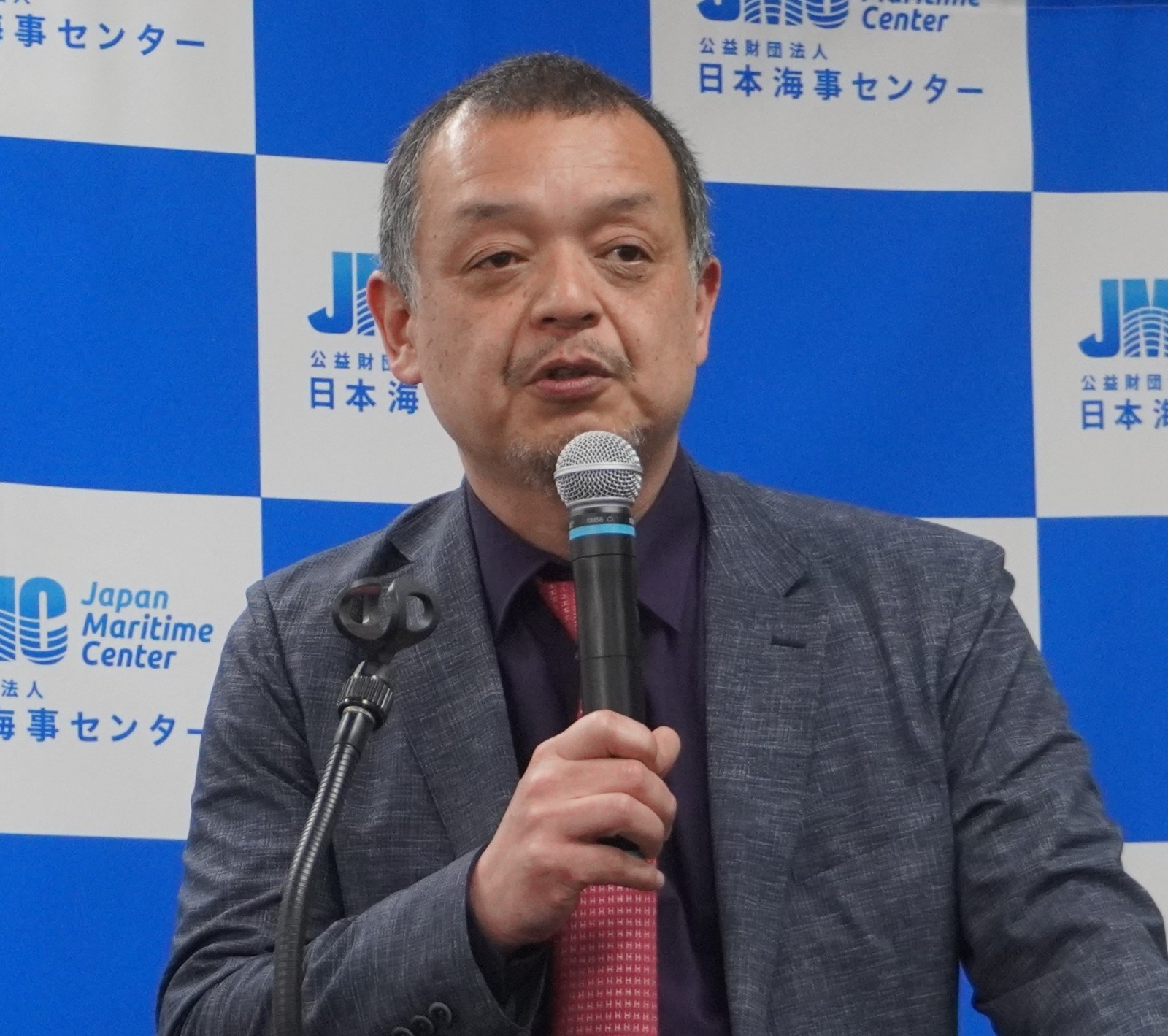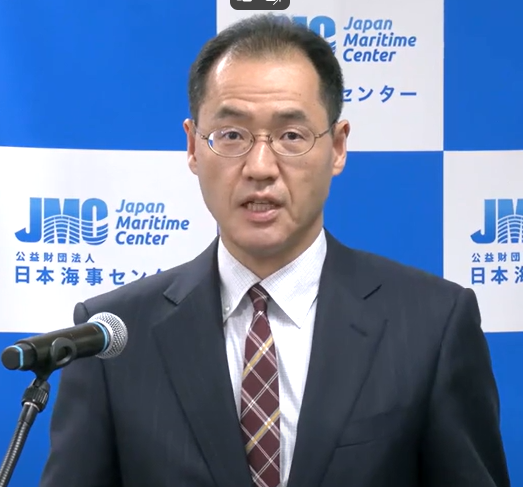第12回JMC海事振興セミナーを開催しました
「グローバルサプライチェーンのグリーン化・デジタル化を目指して ~シンガポール・韓国・中国・日本の取組みと海運・港湾の連携の強化~」
 |
|
 |
|
| 開催概要 | グローバルサプライチェーン全体を脱炭素化することが急務の課題となる中、年間約8億トンのGHG排出量を出す国際海運はもとより、海運と港湾が一体となって脱炭素化を進める取組みである「グリーン海運回廊」を実現・加速していく必要があります。また、航路全体のグリーン化と並行してデジタル化も進めていく必要があります。 今回のセミナーでは、グリーン化・デジタル化に向けて取り組むシンガポール・韓国・中国・日本の動向について紹介するとともに、日本の海事・港湾の関係者をお招きして、意見交換を行いました。 |
| 日時 | 2025年4月24日(木) 14:00 ~ 16:00 |
| 開催方法 | ハイブリッド形式(Zoomウェビナー併用) |
| 開催場所 | 海事センタービル4階会議室(東京都千代田区麹町4-5) |
| 主催 | 公益財団法人 日本海事センター |
| 開会挨拶 | |
| 講演 | |
| 講演 | |
| 講演 | |
| パネルディスカッション(発表) | |
| パネルディスカッション(発表) | |
| パネルディスカッション(質疑応答等) |
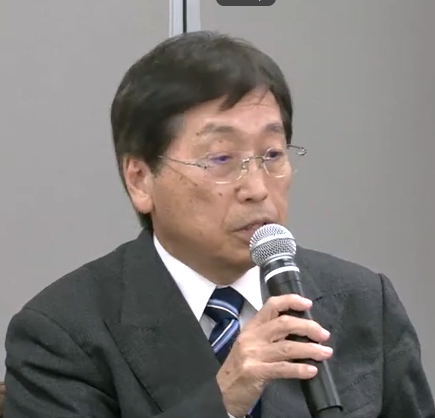 モデレーター:(公財)日本海事センター客員研究員 福山 秀夫 |
| 閉会挨拶 | |
| セミナー動画 (通し) |
https://www.youtube.com/watch?v=4IMJp5ba8Xo |
第12回JMC海事振興セミナーを開催しましたの開催結果(概要)
1.開催の概要
令和7年4月24日、東京都千代田区麹町の海事センタービル4階会議室において、第12回JMC海事振興セミナーを開催した。 当日は、「グローバル・サプライチェーンのグリーン化・デジタル化を目指して ~シンガポール・韓国・中国・日本の取り組みと海運・港湾の連携の強化~」 と題して、ZOOMを活用したオンライン配信を実施し、300名を超える視聴者から参加登録をいただき、盛況裡の開催となった。
2.講演内容
【開会挨拶】 (公財)日本海事センター 会長 宿利 正史 (別添参照)
◎「シンガポールの港湾におけるGX、DXの取組の動向 ~グリーン・デジタル海運回廊への対応と日本の港湾の取組も含めて~」
神戸大学大学院海事科学研究科教授 杉村 佳寿 氏
杉村氏は、「港湾関連のCO2排出は船舶,港湾活動,背後圏輸送からの排出によるものに分類され、背後圏輸送、船舶、港湾活動の順に排出量が多い。CO2排出量削減は、グローバル・サプライチェーンの取組みによって達成される可能性があり、海上輸送と内陸輸送をつなぐ結節点である港湾は、サプライチェーン全体を最適化しうる役割を持つ。このため港湾は,自身のCO2排出量を削減するための戦略を適用するだけでなく、海運や内陸輸送の排出量を削減するための対策を実施できる。」として、グローバル・サプライチェーンにおける港湾の気候変動対策への貢献の大きな可能性について指摘した。代表的な対策は、陸電供給システムや電動式荷役機械の導入ではあるが、港湾業界ではまだ広く採用されている排出削減対策がなく,IMOやIAPHが表明している野心的な排出削減目標と現在の対策の採用状況の間にギャップがあり、世界的にも長期的な努力が必要な状況であるとして、港湾の環境対策が成果を上げるためには、時間がかかるということである。また、先進的な港湾としてよく取り上げられるのは、アントワープ、ロッテルダム、ロサンゼルス/ロングビーチ、ハンブルグ、シンガポール等で、日本が取り上げられることはないということで、日本港湾の立ち遅れを指摘した。一方で、日本は、既に、グリーン・デジタル海運回廊の協力に関する覚書として、国土交通省とシンガポール運輸省間に、グリーン・デジタル海運回廊の協力に関する覚書を令和5年12月16日締結していることも紹介された。
シンガポール港の動向については、シンガポール港当局が、トゥアス地区に新ターミナルを建設しており、最終的に全ての機能をトゥアスターミナルに集約し、2040年代の最終完成時には,世界最大級の完全自動化ターミナルにすることを計画していることに触れ、規制・政策を担当するMPAが、2022年Maritime Singapore Decarbonisation Blueprint: Working Towards 2050を発表し、MPAが注力する7つの重点分野として、①港湾ターミナル、②国内港湾船舶、③将来の船舶燃料・バンカリング基準・インフラ、④シンガポール船籍、⑤IMO等の国際的なプラットフォームにおける取組、⑥研究開発と人材、⑦炭素意識・炭素会計・グリーンファイナンスを挙げ、2050年までにカーボン・ニュートラルへのロードマップを発表して、GX推進を鮮明にしたとし、ターミナルオペレーターであるPSAコーポレーションとJurong Portが,港湾運営に伴う総排出量を2030年までに2005年比で少なくとも60%削減し、2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成することを目指しており、電化+グリーン電力、水素の活用が具体的な方策となると述べた。
杉村氏は、このようなシンガポール港が打ち出した施策は、日本の政策と変わらないが、日本の問題点は実効性にあると指摘した。そして、MPAの基本姿勢を次のようにまとめた。
世界の海運業界が最終的にどの低炭素・ゼロカーボンの船舶燃料を採用するかについては、かなりの不確実性が残るが、MPAは、水素とそのキャリア(アンモニア,eメタノール)、バイオLNGが中長期的に国際海運の脱炭素化において重要な役割を果たす可能性があり、海事産業界と協力し、多燃料への移行を可能にすることを約束し、海運業界のバンカリング需要を支援するとして、シンガポール政府の海運業界への積極的な支援を明確にしているとした。
杉村氏は、DXについては、digitalPORT@SGが、運用されており、DXはGXを支える重要な手段とし、例えば、デジタルプラットフォームを通じた寄港の効率的なスケジューリングにより、船舶のアイドリング時間が短縮され、効率的なサプライチェーンが実現すれば、港湾や船舶の排出量削減に繋がることを指摘した。
次に、日本のカーボン・ニュートラルポート構想については、「港湾脱炭素化推進計画」があるが、絵にかいた餅になる可能性があるとの懸念を示し、日本における先進地域博多港で2010年に政府の実証実験等によりハイブリッドSC、RTG電動化、屋根付きリーファー設備を導入したが、結局、全国には広がらなかったと指摘した。その理由としては、コスト問題があるとして、本体導入費用が高額でエネルギーコストは下がっても不採算という結果が出ていること、これを船社、荷主に転嫁すると港湾競争力喪失の可能性があるという厳しい環境があることを指摘した。さらに、日本の実効性が低い理由として、経済性を要因として本格的な導入には至っていないこと、環境政策において歴史的に規制的アプローチが採られていないことを挙げ、さらに、日本の港湾ガバナンスの大きな特徴として、港湾管理者が商業化・企業化せずに地方自治体が港湾管理権を有していること、多くの港湾では民営化が進んでいないこと、Global terminal operator (GTO) の進出がないことなどを指摘した。つまり、企業化していない港湾管理者には,CSR,ESG経営の動機がなく、地方自治体が港湾管理者としては、中央政府が政策を策定しても、地域の利益が優先し実効性が伴わないことや、ビジネス的視点の欠如といった帰結をもたらすと考えられるからであるとした。GTOが進出していないことによって、諸外国レベルの気候変動対策がターミナルオペレーター主導で進められる可能性も否定されることになるとも述べている。杉村氏は、結論として、日本の港湾は、荷主のCO2排出に対する意識改革が急速に進展しない場合は、諸外国以上に政府のイニシアチブが重要であると指摘し、さらにカーボン・ニュートラルを実現するには、どのような過程で向かうかが重要となると指摘している。
◎「韓国におけるGX、DXの取り組み動向 ~グリーン・デジタル海運回廊などへの釜山港の対応を中心に~」
釜山港湾公社 日本代表部 朴濟晟 (パク ジェソン) 氏
朴氏は、最初に、釜山港の現状として、日本に近いこと、世界第2位の積み替え港であること、2024年取扱量24,402TEU(前年比5.4%増加)であることを説明した。
次に、釜山港のDX推進状況として、簡単に歴史を振り返り、釜山港のデジタル化が、1992年の PORT-MIS 導入に始まり、2005年の BPA-NET 導入によって更新され、2020から、 B2B(Business to Business)、B2C(Business to Customer)中心、効率中心に進化し、2021年に釜山港のデジタル化中長期ロードマップ 「釜山港スマート港湾構築戦略」が発表されたことを説明した。そしてこれからは、Chain Portalによるターミナル業務のデジタル化促進が重要であると語った。その概要を以下の通り説明した。
Chain Portal導入:
機能1 (VBS, 車両予約システム) :車両予約による混雑時間分散 (2022年~)
機能2 (TSS, 積み替え輸送システム):(Group Order機能)トラックと貨物のマッチングによる輸送効率の向上 (2023年~)
機能3 (e-Slip) :ターミナル内のトラック運転手の未降車プロセスの構築 (2024年~)
釜山新港のターミナルゲート、トラックが到着するとRFIDがナンバープレートを認識し、わずか3秒足らずでゲートバーが開く。e-Slipは、搬入・搬出するコンテナの固有番号とサイズ、位置、現在の作業進行段階まで全ての情報を一目で確認できる一種の通行証。
機能4 (Port-i:Transship monitoring system):1つのsystemに釜山港の積み替えデータを集約 → 迅速な積み替え作業可能 (2025年~)
三番目に、釜山港のGXの推進状況について次のように説明した。釜山港のGXは、政府(海洋水産部)とBPAを中心に政策を強化中であり、2050年、釜山港脱炭素推進戦略 (’23.2)として、2050 釜山港炭素Net-Zero達成を挙げ、港湾装備の低炭素化として、釜山港の荷役装備の95%以上を低炭素装備に切り替え、大型船対象高圧AMP(陸上電源供給設備) 29箇所、小型船対象低圧AMP78箇所の設置によるAMPの拡大を行っている。
釜山港のバンカリングの競争力については、バンカリング価格は予想より安いが、課題がまだまだ多いというレベルであり、世界4大バンカリング港には入っていないと述べた。
4大バンカリング港とは、バンカリング供給量基準で、UAEのフジャイラ、米国のヒューストン、シンガポール、ロッテルダムである。韓国最大の石油化学産業団地が蔚山港にあり、釜山港は、世界4大貯油施設を保有している蔚山港から供給を受けているため、アジア60地域の中でもバンカリング費用は意外と安い。LNG、メタノールのバンカリングは蔚山港と連携し、環境にやさしいバンカリング相互協力業務協約を2023年11月に締結した。
朴氏は、最後に、釜山港グリーン回廊の現状について、海洋水産部は、様々な政策を発表しているが、まだまだ初期段階であり、韓国政府が、各国政府と展開しているグリーン回廊構築協力について展開している4つの事例を紹介した。
①(米国)2027年までに太平洋横断グリーン回廊(メタノール燃料)の運航を目標
- Busan / Ulsan ↔ Seattle / Tacoma 間の①コンテナ船航路、②自動車運搬船航路を予備的なグリーン回廊に選定
- 2025年より環境対応燃料の供給技術などに関するR&Dおよび実証事業推進予定
②(オーストラリア)水素・アンモニアのsupply chainを構築中のオーストラリアとグリーン回廊を形成。2029年上半期にグリーン回廊の構築目指す(メタノールまたはアンモニア燃料船を投入予定)
③(シンガポール) 韓国・シンガポール・欧州を結ぶ「メガグリーンシッピングルート」の構築を推進中
④(デンマーク)研究機関間の交流を通じてゼロカーボン船舶の実証・普及を進め、技術の協力を強化
朴氏は、これらの事例を基に、グリーン回廊展開には以下の5つの課題があると指摘した。
①高い燃料コスト
②グリーン燃料に対する低需要
③バンカリングインフラの不足
④技術的未成熟 (アンモニア、水素など)
⑤安全規定及び法規制の未整備
さらに、グリーン回廊運用に関する合意の問題があると指摘し、船社-ターミナル間の契約が複雑な中、安定的な利用が可能かどうか、荷主がGXに伴う費用を支払う意思がない場合はどう対応するかという2つの問題を挙げた。将来的にこれらの諸課題と諸問題に対応を迫られることになるということで締めくくった。
◎「中国におけるGX・DXの取組とSITCの実践」
SITC INTERMODAL JAPAN社長兼SITC LOGISTICS営業総監 呂 開献(ロ・カイケン)氏
呂氏は、最初の大テーマとして、「中国のスマート港湾建設 GXとDX」と題して、第一に、スマート港湾構築の背景に触れ、従来の港湾が世界貿易の拡大に伴い、運用効率、安全管理、環境保護の要件の面で課題に直面している現実を挙げ、それに対応するために、中国のスマート港建設が、近年大きな進歩を遂げたと分析している。そして、中国のスマート港が、5G、人工知能(AI)、ビッグデータ、モノのインターネット(IoT)などの最先端技術を活用し自動化、デジタル化、インテリジェント化を推進して港湾をアップグレードすることで運用効率の向上やコストの削減を実現し、グローバル・サプライチェーン管理を最適化しており、これらを支えるため、中国政府がスマート港湾の開発を支援するにあたり次のような政策を導入しているとして、以下の計画や指針を挙げた。
・『現代総合交通システム発展のための第14次5カ年計画』:スマート港湾と自動化ターミナルの建設を加速する
・『交通強靱化大綱』: 港湾情報のレベル向上のためにデジタル技術の活用を重視する
・『湾陸上電力サービス課金基準及び管理措置』: グリーン港湾の開発を促進する
次に、スマート港湾の代表例に触れ、完全自動化コンテナターミナルが建設中または建設済みである港湾として、青島港、上海洋山港第4期、寧波舟山港、大連港、厦門港、深圳港を挙げ、これらのスマート港湾の開発動向として、4つのポイントを挙げた。
①陸上電力供給(陸電)と新燃料船の燃料供給体制の構築により、陸上から必要な電力を供給することで、船舶からの温室効果ガス排出を抑える
②グリーン海運回廊を導入して、グリーンでスマートな港湾の建設を推進し、炭素排出ゼロのスマートターミナルを開発する
③モーダルシフトを推進し、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換を図り、一帯一路政策により、中国主導のチャイナランドブリッジルートである 『中欧班列』を用いた鉄道との接続を実現する
④5G+AIの導入により、よりスマートな港湾管理を実現し、Deep Seekブームに乗り、新AI技術の利用を加速する
次の大テーマとして、「中国港湾・海運協力」と題して、次の4つの項目が、中国で取り組まれている現状を説明した。
一つ目は、業務運営レベルでの緊密な連携として、情報共有プラットフォームと業務調整会議についてである。情報プラットフォームとは、船舶管理システム、コンテナ追跡および貨物循環システム、船舶申告、貨物申告、料金決済などの情報をEDIシステムを通じて共有して手作業を削減することである。業務調整会議とは、ピーク期間のスケジュール設定、危機対応の調整などである。
二つ目は、多次元協力メカニズムであるが、これには契約及び合意の協力と共同技術開発に関する港湾と海運会社の共同技術革新の推進の2つがあり、前者では、船舶の停泊、貨物の積み下ろし、ヤードの使用などのサービス契約の内容決定、柔軟な価格メカニズムという料金ポリシーの採用などがあり、後者では、新しい航路、物流パーク、コンテナターミナルプロジェクトの共同開発などの戦略的協力協定の締結などがある。
三つ目は、業界コミュニケーションメカニズムであるが、これは、中国港湾協会と中国船主協会及び国際海運同盟(アライアンス)の提携により、港湾と海運会社が、業界団体や提携プラットフォームを通じてコミュニケーションと協力を行う仕組みである。
四つ目は、政府の政策調整であり、これによる港湾や海運会社は地方自治体と連携し、税制優遇やインフラ支援などの政策を実現する。また、共同インフラ計画等の政府参加の仕組みがある。中国では、以上のように中国港湾と海運協力を通じて、GX、DXが強力に推進されているのである。
呂氏は最後に、GX、DXにおけるSITC GROUPの実践に関し、以下の通り、様々な情報を資料と動画等で提供した。
〇専門物流
・SEA&RAIL
中国の各都市とヨーロッパの主要都市を鉄道で繋ぎ、従来の海上輸送のトラジットタイムを大幅に削減する輸送ルート。
・SITC COWIN コイル専用コンテナ
2014年から、SITC COWINはコイル専用の新型コンテナを研究開発してきた。コンテナ内部特有のV字溝の構造を利用することで、従来のコンテナでのラッシング時に発生する大量の材料と人的コス トを削減。
〇SITCが取り組んでいる設備紹介として以下のものがある。
「新エネルギーコンテナフロントクレーン」(電気、水素)
「新エネルギーコンテナスタッカー」(電気)
「水素燃料レール式ガントリークレーン(レールクレーン)
「水素燃料タイヤ式ガントリークレーン」(タイヤクレーン)
「インテリジェントトランスポートカー」
ダブルで40フィート重量コンテナの運搬能力を有する、世界初のアルミ合金フレームで、軽量化構造設計の純電動 & 水素動力のデュアルパワーモードのAGV。
L4融合ナビゲーション技術 & パッシブRFID冗長ナビゲーション技術を装備する。
「スマートポートデジタルツインシステム」
港湾の基盤設備をモデルに、実際の作業プロセスを基に、先進的なIT技術を活用して3Dの港湾モデルと作業シミュレーションを構築するもの。港湾のリソースと作業プロセスのリアルタイムな可視化監視を実現し、 伝統的な港湾をデジタル化されたスマート港湾への転換を支援する。
Single-deck Smart Depot(青島SITC自動デポ)の概要
Area :22000 ㎡ ;
Max storage capacity :8400 TEU;
Efficiency per hour :200 move;
Building height :< 42 m;
Floors of the building: 1 Floor ;
Single stack height :10 containers ;
◎「グローバル・サプライチェーンのグリーン化・デジタル化を目指して 」
国土交通省大臣官房審議官(海事・港湾・危機管理)堀 真之助 氏
堀氏は、グリーン・デジタル海運回廊に関する、日本政府の取組などについて、簡単に紹介した。 グリーン海運回廊については、2021年9月のQUADや同年11月のクライドバンク宣言、2023年6月のG7伊勢志摩交通大臣会合など、様々な場において、グリーン海運回廊の設立を支援していく旨を関係国で合意している。
2023年3月には、米国カリフォルニア州と覚書を締結した。覚書においては、ロサンゼルス港と横浜港・神戸港を結ぶ航路でのグリーン海運回廊の発展に向けて、港湾の脱炭素化に関する共通の取組を進めることなどを謳った。
2023年10月には、ロサンゼルスにおいて、国土交通省とカリフォルニア州運輸省の共催により、シンポジウムを開催し、政府のみならず、各港湾の代表者が出席して取組を発表するなど、協力関係を深め、また、神戸港や横浜港が、それぞれカリフォルニア州の港と個別に覚書を締結するなど、連携の取組が進められた。
一方、2023年12月には、シンガポール運輸省との間で、グリーン・デジタル海運回廊の協力に関する覚書を締結し、グリーンのみならず、デジタル化の促進により、効率性の向上を図っていくこととした。この覚書を受け、シンガポールとの間では、分野ごとにプロジェクトチームを作り、日本とシンガポールの政府や港湾関係者、民間企業の方々も入っていただいた協議を実施しているところである。
方針としては、我が国においては、カーボン・ニュートラルポートの形成を目指しており、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を図ることにより、荷主や船社から選ばれる競争力のある港湾を形成していきたいと考えている。そのため、2022年に港湾法を改正し、港湾管理者が「港湾脱炭素化推進計画」を策定することができる仕組みを導入したが、これを受け、京浜港・阪神港といった国際コンテナ戦略港湾を含む多くの港において協議会が設立され、計画の策定も順次進んでおり、今年度からは、港湾のターミナルの脱炭素化の取組を政府が評価する「CNP認証」の制度を創設し、コンテナターミナルの脱炭素化の取組の透明化を図り、客観的に評価することにより、取組を促進していく所存である。
カーボン・ニュートラルポートに関する具体的な取組として、政府は、水素を燃料とする荷役機械の導入、LNGバンカリング拠点の形成、陸電の導入などへの支援を行う。
一方、船舶についても、グリーンイノベーション基金を活用し、水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船のコア技術となるエンジン・燃料タンク・燃料供給システム等の開発・実証を実施するなど、船舶の脱炭素化への取組を進めているところである。
◎「グリーン・デジタル海運回廊の現状とONEの取組み」
オーシャン・ネットワーク・エクスプレス ジャパン株式会社代表取締役 社長執行役員 戸田 潤 氏
戸田氏は、ONEのグリーン戦略:脱炭素化に向けたVision、Mission、目標と環境対策として、7つのイニシアチブがあると説明した。それは、①グリーン投資、②代替燃料、③カーボンマネージメント、④効率的なオペレーション、⑤エコシステムの構築、⑥クリーンなシップリサイクル、⑦環境保護である。 戸田氏は、ONEによるGHG削減サービスであるONE LEAF+は以下の特徴をもつと紹介した。
Step 1 : グリーン燃料を用いてGHG排出量を削減
Step 2:CO2換算削減量をストック
Step 3:希望されるお客様へ販売し証明書を発行
顧客のために、ONE LEAF+の利用で最大84%までGHG排出量削減が達成可能
次に、戸田氏はONEが参画している2つのグリーン・デジタル回廊について次のように解説した。
・ROT - SIN Green & Digital Shipping Corridor( Rotterdam – Singapore Green & Digital Shipping Corridor)
・LA – Shanghai Green Shipping Corridor
現在、世界では10万隻の商船が運航され、年間3億トンの燃料を消費(= 世界全体の炭素排出量の約3%)、IMO目標は、2030年までにGHG排出量を20%低減である。ROT - SIN Green & Digital Shipping Corridor が目指すものは、2030年に約20%の燃料を持続可能な代替燃料に転換し、2028年には8000個船以上の本船200隻以上が代替燃料を使用して、2030年までに参加船社の本船キャパシティーの約25%までが代替燃料に転換が可能となる。ONEはGreen Shipping Corridorに参画する目的追加費用の負担及び補助スキーム等海運における脱炭素化の標準モデルの構築を進めている。
<多様なステークホルダーとの多層的な連結性の強化が必要>ということで、次のことが実施されている。
・代替燃料船の運用促進
・代替燃料の供給体制の構築
・ゼロエミッション船の(アンモニア/水素燃料船)技術開発
・荷役器機の低・脱炭素化、ヤード内照明のLED化
・停泊中船舶への陸上電源供給
・書類や手続きの簡素化・電子化
・関連する法整備
・追加費用の負担及び補助スキーム、など。
次に、戸田氏は、最大のボトルネックは代替燃料の価格であることを指摘し、代替燃料の需給において「ニワトリ vs たまご」問題を誘引すると、危機感を示し、下記のような事情を説明した。
【供給側の事情】
供給体制の整備には莫大な投資と時間が必要。確かな需要の見極めが困難な現状⇒投資を計画・実行することが容易でない。
【需要側の事情】
戸田氏は、潜在的な需要はあるものの、供給体制が整っていないため、十分な量の代替燃料を、適正な価格で、求められる場所で調達するのが容易でなく、また、現在限られた数量の代替燃料が超高価格で取引されており、単一の業界や企業のみで解決できる課題ではない。業界・企業間の協業、行政や世論のサポート、市場の成熟⇒追加コストは受益者が負担するなどの原則を確立する必要があると指摘した。
結論として、Green Corridorとして期待されるものは、低炭素化オペレーション、安全性の確保、標準化された証明書、さらに、早期の商業化実現の為のスキーム、資金調達オプションの構築、広範囲の低・脱炭素化の為の知識や学びのテコ入れであるとした。
【パネルディスカッション】
モデレーター : 日本海事センター客員研究員 福山 秀夫
パネリスト :
神戸大学大学院海事科学研究科教授 杉村 佳寿 氏
釜山港湾公社日本代表部 朴 濟晟 (パク・ジェソン) 氏
SITC INTERMODAL JAPAN社長兼SITC LOGISTICS営業総監 呂 開献(ロ・カイケン)氏
国土交通省大臣官房審議官(海事・港湾・危機管理) 堀 真之助 氏
オーシャン・ネットワーク・エクスプレス ジャパン株式会社代表取締役 社長執行役員 戸田 潤 氏
◎モデレーターから堀様への質問
日本政府の取組の状況等がよく理解できました。シンガポール、中国、韓国の取組に関する3人の方からの講演を聞いていただきましたが、将来的に日本が、これらの港湾との競争力を高めるために、どのような取組を優先して行うべきだとお考えでしょうか。
(ご回答)
本日は、貴重な機会をいただき、感謝いたします。シンガポール、韓国、中国のいろんな取組を紹介していただきました。それぞれの国で置かれた条件が異なるものの、日本でもっとここに力を入れなければならない点を見せていただきました。広く世界に視野を広げて日本の取組を見直すいいきっかけになりました。(この後退席)
◎モデレーターから戸田様への質問
次に、戸田様にお尋ね致します。これからは、グリーンソリューションが、荷主への最重要な営業サービスになるということでしたが、荷主の理解や港湾との協力は進んでいくとお考えでしょうか。課題になることがあれば教えてください。また、DXの取り組みの内容についてもご説明をいただき、課題になることも教えて下さい。
(ご回答)
大きな視点では我々の顧客である荷主さんの製品についてその生産、輸送、販売というサイクルにおけるGHG排出量削減が求められますが、我々海運会社はその一連のプロセスの中で海上輸送に関する部分について海運会社としてのグリーンソリューションをご提供できるよう、取り組んでいるところです。同時にコンテナ海上輸送に非常に近い関係先としてコンテナターミナルのオペレーターさんがいらっしゃいます。ターミナルでのGHG排出量削減についても現在取り組みが進んでおりますが、これらの取り組みについてはコンテナ海運会社として共に議論を重ねて取り組んで参ります。また、これらコンテナターミナルオペレーターとコンテナ海運会社による協業について、すでに多くの荷主さんからご支持をいただいていますが、先に申し上げました通り代替燃料については割高な商品であるというのが現状です。この状況を少しでも改善するべく取り組むことにより、荷主さんからのより一層のご理解、ご支援をいただけるものと確信しています。
海運においてもDXの取組みは最重要課題の一つとして、次世代ビジネスに向けて日々着実に進展しています。運航においてのDXがもたらすメリットとして、将来的に拡張現実(AR:Augmented Reality)技術による操船のサポートシステムが充実すれば、船員不足を解決する糸口となることが期待できます。システムサポートによって安全且つ効率の良い航行が可能となり、結果的にヒューマンエラーをなくして航行の安全性が高められます。自動操船や遠隔操船といった技術革新が進めば、危険な海域には人が乗船しなくても航行を可能となり、また、通常ルートの平易な運航便にも無人運航便を加えていくことで、限られた人数の乗組員による効率的な運航が可能となります。
◎モデレーターから杉村様への質問
次に、杉村様にご質問いたします。シンガポール港での取組みと日本のカーボン・ニュートラルポート構想の違いと日本の港湾への期待もお聞きしたいと思います。さらに、グリーン海運回廊という港湾と船社の協調・提携による狙いや目的というのがはっきりしていないという指摘があります。そもそもどのような狙いでどのような効果が期待できるのか、簡単に解説をお願いできればと思います。
(ご回答)
カーボン・ニュートラルに向けたシンガポール港の計画と、日本の港湾脱炭素化推進計画については電化、再エネ、水素などがキーワードであり大きな違いはありません。問題は実効性であり、シンガポール港の場合は財政的な支援を中心に政府のイニシアチブが強い。日本も各種ガイドラインの整備や港湾法改正で港湾脱炭素化推進計画を法定計画化するなど計画策定面では政府のイニシアチブは発揮されているが、計画に実効性を持たせるためのイニシアチブを期待したい。気候変動対策の導入には金がかかります。それを誰が負担するのかが大きな課題です。荷主の意識改革が進展すれば港湾競争力確保のために各港湾が自主的に対策を導入する可能性がありますが、そうでなければ財政的な支援が必要になるケースも出てくるはずです。
港湾と船社の協調・提携については、そもそも海運のGXを考えるとき、港湾と船社を分けて考えるのはおかしいと思います。講演の中でも説明した通り、ドア・トゥー・ドアで考えれば、港湾活動による排出は微々たるもので、大部分は船舶からの排出です。しかし、港湾は出入りする海運、陸運に対して脱炭素化を求めうる立場にあります。これがまず重要です。次に、大企業である船会社は必ず脱炭素を達成します。将来的に荷主の脱炭素意識が高まると想定すれば、ドア・トゥー・ドアで考えたとき、港湾の取組みが遅れれば、港湾におけるCO2排出のシェアが高まり、CO2排出量の多い港湾を船舶が敬遠する可能性もあります。場合によっては非効率な経路になります。これは日本経済にとって不幸な話です。それぞれが影響を与える立場であることを理解し、港湾と船社は、足並みを揃えて対策を講じていく必要があります。船社はネットワークを形成して活動するので、グリーン海運回廊には、港湾と海運を含む広域的な海事産業全体の脱炭素化の取組みが必要だというメッセージが含まれていると考えれば理解しやすいと思います。
◎モデレーターから呂様への質問
さて、次に、呂様に質問いたします。中国ではシンガポール港と異なり、T/S貨物だけでなく、貿易品の輸出入が盛んです。港湾と海運の連携で、「ビジネス調整会議メカニズム」や「戦略的開発メカニズム」など政府参加の仕組み等についてSITCはどのようにかかわっておられるのか、また、日本の今後の取組へのアドバイスがありましたら、お願い致します。
(ご回答)
中国では各港の建設と開発において中央政府の交通部と自治体港湾局によるダブル行政管轄系統の下で、実際の港湾運営は国有企業としての◯◯港有限公司によって執り行われます。バースウィンドや着岸時間の配分など全て専門部署で管理し、運航船社を招集し、定期的に会議を開催して港湾管理効率を高めます。SITCも各港ブランチを通じて、この港湾管理のプラットフォームに参加して日々の航路運航状況を共有します。また、各級船主協会は船の運航会社の集まりという意味にとどまらず、人的配置などで行政の意思を業界に積極的に取り入れ、船会社の第一線の経営状況も政府に伝達し、政策立案に役立たせます。
また、上海航運交易所(SSE)のような機構は海運港運業界に必要な経済情報データやマーケット状況の取りまとめを行い、運賃指数などを、定期的に公表して、広範囲に海運、港湾経営をサポートしています。SITCもこれらの業界機構の活動に積極的に参加しています。
また、中国各港の「一帯一路」「出海戦略」の枠組みのなかで、SITCは東南アジアに構築したネットワークを生かして、この地域の各港と中国各港との架け橋になって、港湾経営者同士の交流と連携をアシストします。」
◎モデレーターから朴様への質問
それでは次に、釜山港湾公社の朴様にお尋ねいたします。釜山港グリーン化については、次世代燃料のバンカリングにおける蔚山港との連携はうまく機能するのかどうかも含めて、もう少し詳しい説明をいただけますでしょうか。
(ご回答)
釜山港は昨年、LNGとメタノールのShip-to-Shipバンカリングを成功裏に開始しました。
今回のバンカリング実証が意味あるのは、バンカリングと荷役が同時に行われた点です。
コンテナ船は別途の時間を設けて燃料を供給される時間的余裕がなく、バンカリングと荷役を同時に行うことが必ず必要です。そして、これを達成するために重要なのは安全性を確保することです。もしLNGバンカリングだけを行う場合にはバンカリング区域だけを安全区域に指定するが、同時作業の場合にはバンカリングだけでなく荷役区域まで安全区域に指定することになります。また、安全性の確保だけでなく、迅速にバンカリングを行うことも重要になるため、作業難易度が高くなります。したがって、同時作業のためには、バンカリング船とコンテナ船間の協議だけでなく、政府、港湾公社、ターミナル運営会社など様々な利害関係者との協議が必要です。
今回のバンカリング実証は成功的だったが、今後は1回性ではなく、定期的なバンカリングのための協議が行われる予定です。そして、このような釜山港と蔚山港の協力を通じてバンカリングを実施することはお互いに有益です。釜山港の立場では、蔚山港を活用して初期インフラ投資に対する問題を解決することができ、蔚山港はバンカリングのための需要を確保することができます。特に、蔚山港は2030年までにLNGとメタノールだけでなく、水素、アンモニアインフラも構築する予定であるため、釜山港は当面、蔚山港と協力してバンカリングの供給を強化していく計画です。
【会場からの質問】
◎戸田様と呂様への質問
戸田様、呂様のお2人にお尋ね致します。グリーン・デジタル海運回廊への対応により、グローバル・サプライチェーンにはどのような影響があるのか、船社の見通しについて教えてください。
《戸田様のご回答》
海運業の立場として申し上げますと、これまでのようなコストや生産効率だけでなく、より環境対応に沿った形でのサプライチェーンの再構築の流れが加速するのではないかと考えます。例えば欧州における調達がこれまでの主要供給元であった中国やアジア諸国、インドから東ヨーロッパや北アフリカに移るといったイメージです。環境対策として輸送距離を短縮するという考え方です。仮にそのようなことになるとしてもコンテナ海運会社としてはその時の輸送需要に適したサービスを提供していくことになると考えます。
《呂様のご回答》
グリーン・デジタル海運回廊の国際協調により、この取り組みは一国、一港湾に止まらず、海上輸送サービスを提供する海運会社、フォワーディング会社は各自のサービスエリアにおいて、広域連携、陸上へのサービスの延伸なども心掛けるようになっております。
例えば、SITCは寄港中の東南アジア地域で積極的に「海陸一体化」と称する独自の海運回廊を構築しています。 一例として、ベトナムのハイフォン港において、船社としてのSITC CONTAINER LINES、輸出入フォワーディングサービスを提供するSITC LOGISTICS、デポサービスを提供するSMARTデポがコラボして、首都ハノイを含む北ベトナム地域で荷主間の輸出入コンテナのマッチング(CRU)を取り組んで、コンテナドレージは空走りの状態を無くして、荷主の輸送コスト(ハイフォン〜バックニンでは20ドル削減)と二酸化炭素の排出量の低減(約50%削減)につながりました。
24年半ばからの取り組み開始でしたが、24年年間輸出入マッチングできたコンテナは69,119 TEUとなり、うち自社手配ドレージサービスは17,786TEUであり、残りはマーケットのドレージサービス利用になります。北ベトナム全体の輸送品質と効率向上でドレージ輸送の収益性に貢献しました。さらにSITCロジグループが出資している、中国国内の港湾でコンテナドレージ配車サービスを提供するJIXINGTONG社はベトナム進出をはたして、地場のマッチングのクォリティーを高めるだけでなく、中国港湾利用中荷主さんに中国にある工場からベトナムのエンドユーザーまでの一貫配車サービスを提供して、ベトナムだけでなく、積み港、揚げ港両サイドのグランドラウンドユースが実験できています。
【Webからの質問】
1)朴様への質問
朴先生に質問があります。
①e-slipシステムを製作するにあたっての費用負担は、釜山港湾公社が全額負担されたのでしょうか。また運用費も、釜山港湾公社が全額負担しているのでしょうか。
②Port-iのシステムは、とても貴重な情報が一覧的に確認できると理解しましたが、どのような方(船社・荷主など)が閲覧可能なのでしょうか。また、情報の編集権限はどなたになるのでしょうか。
(ご回答)
e-slipは釜山港湾公社の予算で開発され、運営も釜山港湾公社で推進中です。e-slipをはじめとする釜山港の港湾物流情報システムは、費用よりも重要な問題はデータを確保することでした。民間企業である船社やターミナル運営会社などでは、企業のデータ情報を共有することに消極的だからです。釜山港湾公社はこの問題をブロックチェーンという技術を活用して解消しました。ブロックチェーン技術を使用すれば、検証された人に検証されたデータのみを提供するため、このような問題が解消されました。したがって、Port-iの場合も、特定の人がデータの編集権限を持つのではなく、検証されたデータだけを見ることができるようになっています。現在、Port-iを使用できる対象は、船社、ターミナル運営会社などですが、荷主も釜山港で貨物の状態など関心があるため、海外荷主にも権限を与えるように本社に問い合わせています。まずは今年、HMMを対象にトライアル使用後、利用対象を他の船社に拡大していく計画であり、その次の段階として荷主も使用できるように検討していく計画です。
2)戸田様への質問
グリーンソリューションを提供するにあたって、多額の投資やコスト負担が発生しますが、ONEだけでは負担できないと思います。そのような負担に対してどのように対応されるのか、計画があればお聞かせください。
(ご回答)
先ほど代替燃料はまだ割高だと申し上げましたが、ご参考までに代替燃料について申し上げますと、外航海運において5000トン以上の本船における現在の化石燃料の消費量2億トンを代替燃料に置き換えると、メタノールの場合で現在の生産量の138倍の供給量が必要と試算されています。したがって今後莫大な設備投資が必要なのだろうと想像されます。このような追加の投資は当然の燃料油価格に反映されますが、これを海運会社だけで負担するというのは持続可能な対応とは言えないのではないかと思います。したがって関係するすべてのステークホルダーの皆さんとの間でシェアできるような仕組みを構築することが肝要だと考えております。その方策の一つとして先に申し上げましたGreen Shipping Corridorを通じて『マーケットプレイス』というコンセプトを導入して、環境対応に伴うコストやリスクに関して可能な限り透明性をもって対応できる仕組みの構築を目指しています。
3)呂様への質問
SITCのコンテナデポの自動化は大変面白いと思いましたが、ほかにどのような自動化の取り組みがあるのでしょうか。また、中国ではそのような流れが一般的なのでしょうか。自動化はどんどん進むとお考えですか。
(呂様のご回答)
実はビデオでお見せしまた青島のコンテナ自動デポは5月の開業予定で、世界初となります。現在、SITC INTELLIGENT TECHNOLOGY社はサプライヤーとして、シンガポール港において自動デポの建設に携わっています。それも年内引き渡しになる予定です。まだ、空バンデポの運用に留まっていますが、将来的に、コンテナ自動ターミナルの更なる発展によって、自動ターミナルに組み入れるようになるのもおかしくありません。自動ではないのですが、SITCはSMART DEPOTというブランドで中国、東南アジアでパブリックのコンテナデポを経営しています。
すでに中国では7港9デポ、ベトナムでは3港5デポ、インドネシアでは3港3デポ、タイでは2港3デポ、マレーシア1港1デポで面積計190万平米におよび、手広くデポサービスを提供しています。海陸一体化の要として、これらのデポはSITCグループのグリーン・デジタル海運回廊構築に重要な役割をはたしていますので、将来的に、時代の流れにそって、自動化にする可能性は十分あります。
◎モデレーターの総括コメント
世界的なサプライチェーンの脱炭素化、つまり、グリーン・デジタル海運回廊の脱炭素化が取り組まれていることが、本日のセミナーで明らかになりました。荷主等のステークホルダーに支持される船社と港湾の協調として、バンカリングの需要への対応と創出、GHG排出量削減、燃料コストの抑制、自動化・AI化による荷役作業の効率向上などが挙げられますが、これらによって、船社のスケジュール遵守率向上や選ばれる港湾の構築などのWin/Winの流れを創出してゆくことが、必要であることがわかりました。そして、これらが、我が国の港湾脱炭素化推進計画等に実効性を持たせることになることが明らかになりました。シンガポールや中国は国の積極的な財政支援を行っています。我が国も施策の実効性を高める財政支援や更なる努力の必要性があることも判明しました。すでに、日本/カルフォルニア州との覚書、ロス/横浜港・神戸港との覚書、シンガポール/国交省との覚書などが締結されており、将来的には、環境対応に沿った形でのサプライチェーンの再構築の流れが加速してゆくものと思われます。カーボン・ニュートラルがいよいよ現実味を帯びてきました。ビジネスの競争条件になってきています。これからは、サプライチェーンの最適化の第一条件は、効率化よりは、脱炭素化、カーボン・ニュートラルということになるものと思われます。以上で、総括コメントを締めくくりたいと思います。
【閉会挨拶】 (公財)日本海事センター常務理事 下野 元也(別添参照)
(注)以上の講演の結果概要につきましては、主催者側があくまで速報性を重視して作成したものですので、発言のニュアンス等を正確に再現できていない個所、あるいは重要な発言が欠落している箇所等がある可能性があります。つきましては、発言の詳細や正確な発言を確認したい場合は必ずYouTubeを視聴してご確認いただくようお願いします。また、本結果概要の無断での転載等は控えていただくようお願いいたします。